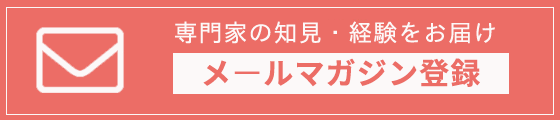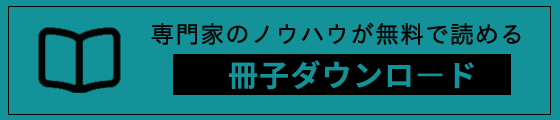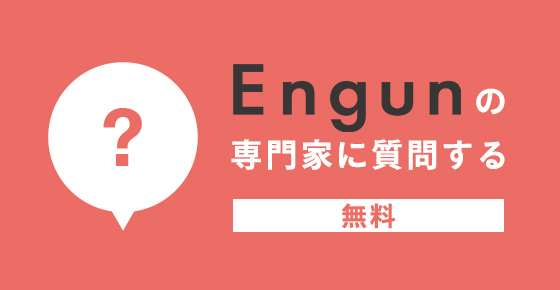生産管理
2019/10/30
中小企業の生産性を上げる「工程管理」。手順や作業の仕方を改善する方法
![[中小企業の生産性を上げる「工程管理」。手順や作業の仕方を改善する方法]トップ画像](https://cdn.2nd-pro.com/media/process-20191031-top.jpg)
コスト競争が苛烈化する昨今、国内製造拠点はコスト競争では不利な海外の製造拠点に負けないようスピードや品質を維持していかなければなりません。
今回は、そんな激しい競争にさらされている製造責任者からの相談に専門家である(株)石川改善技術研究所の石川雅道氏がお答えします。
中小企業からのよくある質問
工場の生産性を上げるために、手順や作業の見直しをしたいと思っているのですが、どこからどのように手を付けたらよいかわかりません。
良い方法があれば教えてください。
この質問に回答する専門家

株式会社 石川改善技術研究所
代表取締役
石川 雅道
家電メーカーにてデバイス・半導体の生産ライン企画、設計、立ち上げなど行いながら、生産性向上を目的とした改善活動も担当。「グローバルよりローカルに」「集中より分散」とものづくり現場を鼓舞するエンジニア。
目次
 中小企業の生産性向上に必要なこと
中小企業の生産性向上に必要なこと

企業経営は、金融機関からの借入金や自己資金で材料を購入し、モノを造っては販売してお金を手にする一連のサイクルで成り立っています。そのサイクルを如何に効率良く回すかが経営の要です。
過剰でも低い品質でもないお客様が要望する品質のものを、如何に素早く供給できるかが競争力を優位にします。量やコストで競うことは誤った方策です。
大事なのは、材料を倉庫に保管する時間や営業・販売情報を収集・操作している時間、加工組立を待つ時間、商品を売れるまで倉庫に滞留させておく時間等々の付加価値を生まない時間を削減することです。受注から納入までの時間(リードタイムと呼ばれる)を短くすることです。
そのためには工場内の仕掛りや在庫を削減し、人や機械のムダな動きを減らして高い生産性を得ることです。そうすることで会社の運転資金を少なくできる企業となります。
 現場のもったいないを徹底的に探す
現場のもったいないを徹底的に探す

働く現場にはまだまだその「もったいない」事象が、多く見られます。作業する人が現場でモノを探したり、モノを積み替えたりの動作はムダであり、「もったいない」動作です。そのムダな動きが、給与の大半を占めている工場は決して少なくありません。
生産性向上には、この「もったいない」時間を徹底して削減し、真の付加価値の時間を増やしていけば良いのです。営業、設計、総務、経理などのあらゆる仕事の領域で、付加価値の時間が増えるように改善を行うことです。
製造現場を対象とすると、人が工具を使って部品を取り付けるその瞬間とか、動かす機械がガチャンガチャンと音を立てて加工する僅かな時間だけが付加価値の時間です。どんなに優れた企業の現場でも付加価値は10%を越えることはありません。
その付加価値の時間の比率を高めれば、短い働く時間で従来と同じ生産数を達成できることとなります。
そのためには、レイアウトを見直して歩行距離を短縮したり、作業手順を変えて動作を楽にしたり、材料を取ろうと伸ばす手の距離を短くしたりという、ごく当たり前な改善の取り組みが功を奏します。
付加価値を高めれば、低労務費の地域にも勝てる
作業現場における人の動きは、作業とムダに分けられます。作業と呼ばれる人の動きは、付加価値とその付加価値を生むためにやむを得ず行う付帯作業とに区分されます。付加価値と認められるのは、モノの形を変えることとモノの質を変えることの二つだけと定義されます。
ムダな動作に作業する人自身は気がつきませんが、必要な工具や材料を探し回る歩行や、前工程からモノが来ないことで生じる手待ちなどが該当します。
 気を付けたい!もったいない自動化
気を付けたい!もったいない自動化

現場で働く人の手の動きは最短の距離を繰り返していますか?まとめて作業する方が良い効率と勘違いして、数十個単位で次の工程に渡していませんか?片手だけで仕事をしていませんか?そうした問題点に“気がつく”ことが必要です。
“気がつく”にはムダをムダとして認識し、それを廃除する基本を学ぶことが必要です。その改善の着眼点として古くから「改善の4原則」「動作経済の4原則」があります。
現場で多くの問題点に“気づき”直ちに改善すれば、高額な設備投資せずとも生産性が上がります。
専門家からのワンポイントアドバイス
流行のIoTだAIだとマスコミの論調に惑わされずに、生産性向上の手段に困ったら基本に立ち返ることです。
 「もったいない」がモノづくりの原点
「もったいない」がモノづくりの原点

日本語の“もったいない”という価値観は、世界各地で取り組まれる環境問題の解決の合い言葉である三つのR「Reduce=削減する、Reuse=再利用する、Recycle=再生する」という概念に、「Respect=尊敬する」という概念を加えたものと言えます。最初に飲み水に使用し、残りを野菜や果物の冷却に使い、さらに汚れ物を洗うという岐阜県郡上市にみられる水船や昔から使われている風呂敷などは、「もったいない」の代表的なシンボルと言えます。
 ムダを減らして海外との競争でも優位に
ムダを減らして海外との競争でも優位に

人の動きや設備の動きを現場に立って観察し、付加価値を生む時間か、ムダな時間かを見分けましょう。現場に仕掛りが多数あれば、ムダな運搬や動作が増えます。完成品を倉庫に保管すると、余計な工数や運搬機器を必要とします。
少ない仕掛り在庫で工場が運営できる「ものづくり力」があれば、海外との競争でも優位に立つことができます。
専門家紹介

株式会社 石川改善技術研究所
代表取締役
石川 雅道
専門分野
□ ものづくり 生産管理(現場改善、在庫削減、ヒューマンエラー対策、設備改善など)
自己紹介
1951年秋田県生まれ。家電メーカーにてデバイス・半導体の生産ライン企画、設計、立ち上げなど行いながら、生産性向上を目的とした改善活動も担当。国内外の設備技術者にIEや安価で小型の設備である「からくり」教育を行う。2009年に創業し、ミラサポ専門家派遣者などモノづくり支援で現在に至る。
「グローバルよりローカルに」「集中より分散」と今時の流行に抗う考え方でものづくり現場を鼓舞するエンジニア。
・この専門家の他の記事をみる
2020/4/2
2020/1/31
・このカテゴリーの他の記事をみる
2020/2/19
2020/1/31