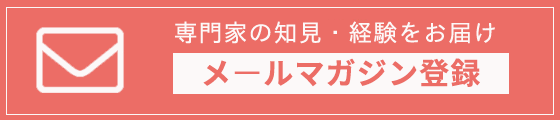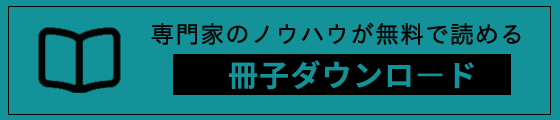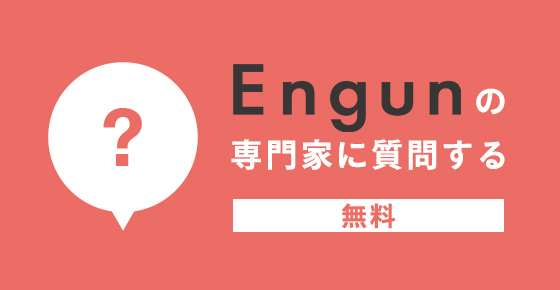人材採用
2019/10/31
中小企業の中途採用は難しい? 良い人材が応募してくる採用情報とは
![[中小企業の中途採用は難しい? 良い人材が応募してくる採用情報とは]トップ画像](https://cdn.2nd-pro.com/media/recruit-20191031-top.jpg)
中小企業にかかわらず、採用するなら良い人材を取りたいですよね。
近年売り手市場が続いていているため、良い人材が大手に流れてしまっているように感じる採用担当者も多いと思います。中小企業にとって厳しい採用状況を打開したいけれど、どうしたら良いかわからない。
今回は、そんな相談に専門家のオフィス ア ライトの杉山達郎氏がお答えします。
中小企業からのよくある質問
採用広告にはそれなりの予算を割いているつもりですが、応募どころか、全く反応がなくお手上げです。会社に知名度がなく、条件も大企業ほどよくないため、あきらめムードです。
どうすればよいのでしょうか?
この質問に回答する専門家

オフィス ア ライト
代表
杉山 達郎
慶応義塾大学卒業後、株式会社ニコン入社。企業におけるさまざまな人事労務課題について、労働者代表としてまた企業経営者として取り組み、現在は「労使がわかる社会保険労務士」と中小企業経営者の支援をしている。
目次
 採用で伝えるべきこと
採用で伝えるべきこと

2017年中小企業白書によると、採用時に企業は「仕事内容・やりがい」「給与賞与の水準」「沿革・経営理念・社風」「業績・経営の安定度」の順で採用者に伝えていますが、求職者が重視した企業情報は、「仕事内容・やりがい」「給与賞与の水準」まで同じ、その次は「就業時間・休暇制度」「職場の雰囲気」「仕事と生活の両立への配慮」となっています。 もちろん、理念や業績も重要です。しかし求職者の知りたいことはそれらよりも、自分が働く労働条件や職場環境を重視していることがわかります。
つまり求職者にとって採用情報として必要なのは、自分が就職した後のワークやライフのイメージであり、それを採用情報として伝えることが重要となります。
 欲しい人材を明確化する
欲しい人材を明確化する

また欲しい人材がはっきりしないと、具体的に誰に誰のワークやライフを伝えていけば良いのかわかりません。人材不足の時代には、女性や高齢者、外国人など採用も多様化していく必要があります。ターゲットに合わせた、採用情報を提供することが必要です。
どんな人材が欲しいのかを明確にするためには、人員計画を作成しておくことです。いつどの部署でどれくらいの年代層の社員を採用し、5年後、10年後にはどんな職域を求めるのかといった計画を作っておきましょう。そうすれば、誰かが退職したからと言って慌てて採用を考える必要はなく、人員計画に沿って、会社の方向性に合った採用活動ができるはずです。 その際には、経営側の一方的な考えで作成するのではなく、現場の要望をヒアリングするなど、経営・人事・現場でよく話し合って、共通の人物像をもつことが重要です。
専門家からのワンポイントアドバイス
採用プロセスでは、書面などで必要な人物像を明確にしておきましょう。それを採用担当者・面接者が共有することで、採用にブレがなくなります。
 ターゲットへのアプローチ方法
ターゲットへのアプローチ方法

HPもぜひ有効に活用したいツールです。そこでは、採用したい人物像にマッチする情報を提供しましょう。それが例えば女性であれば、どうやって育児と仕事を両立させているか、女性のキャリアプランはどうなっているかなどを、女性社員に語ってもらいましょう。また若手社員を採用したいのであれば、年の近い社員に残業の量や就業後・休日の過ごし方、どうやって上司に有給休暇の申請をしているかなど、身近な関心事を話してもらうと良いでしょう。
 積極的に活用したい「リファラル採用」
積極的に活用したい「リファラル採用」

リファラル採用はいわゆる縁故採用で、採用候補者として社員の知人・友人を紹介してもらう制度です。
メリットは、社員が会社と知人・友人双方を理解しているためマッチング率が高いこと。また事前に状況を相互が理解できることから、採用後のミスマッチも起きにくくなることです。一方デメリットは不採用になった場合、その社員との人間関係が気まずくなる恐れがあることです。これには会社が十分配慮してあげる必要があります。
また、会社が紹介する社員に何らかの報酬を支払う場合は、職業安定法40条・労働基準法6条に抵触しないように注意が必要です。具体的には監督署や社労士に確認すると良いでしょう。
 中小企業の中途採用のコツとは
中小企業の中途採用のコツとは

しかし昨今の求職者は給与面の労働条件だけでなく、労働時間や職場環境・人間関係なども企業選択の際に重視しています。すべてにおいて大企業が上回っていることはなく、中小企業だから柔軟に対応できていることもあるはずです。
自社のできていることを積極的に開示し、できていないことはできていないとしたうえで将来の考えを説明してあげればよいと考えます。
求職者の知りたいことはリアルなワークとライフです。そして、それを伝えることで将来のミスマッチも防ぐことができるはずです。

専門家紹介

オフィス ア ライト
代表
杉山 達郎
専門分野
□ 人事・賃金制度の設計・構築、運用改善
□ 働き方改革制度導入・運用提案
□ 人事労務を中心とした経営管理支援
自己紹介
慶応義塾大学商学部卒業後、株式会社ニコン入社。グループ会社である株式会社那須ニコン代表取締役、株式会社ニコン・エシロール執行役員生産企画ゼネラルマネジャー、オプトス株式会社取締役経営管理部長などを歴任。30代には、会社を休職しニコン労働組合中央執行委員長も担当。現在はニコンを早期退職し、オフィス ア ライト代表へ。企業におけるさまざまな人事労務課題について、労働者代表としてまた企業経営者として取り組んできました。その経験を基に、現在は「労使がわかる社会保険労務士」として中小企業経営者の支援をしている。
・この専門家の他の記事をみる
2020/5/16
2020/3/11
2020/1/30
・このカテゴリーの他の記事をみる
2020/5/16
2020/5/10