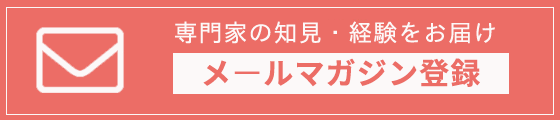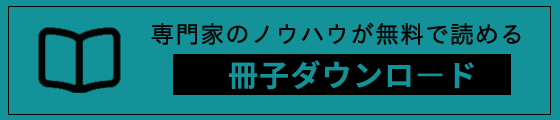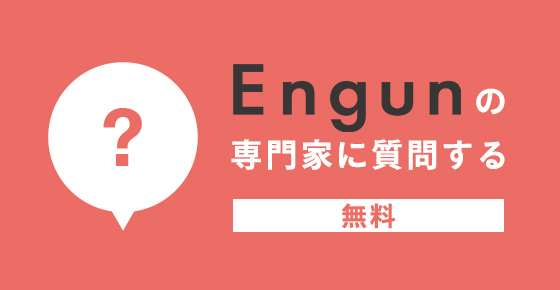経営企画・戦略立案
2019/12/27
中小企業がムリなくできる、コスト削減の考え方と進め方
![[中小企業がムリなくできる、コスト削減の考え方と進め方]トップ画像](https://cdn.2nd-pro.com/media/697b6df49ee9f74018ff53a6eb5201f7_s.jpg)
事業ではヒト、モノ、カネなどを動かすためコスト発生は避けられません。しかし、無駄なコストを削減することで利益を改善することができます。またコスト削減のためのちょっとした工夫による業務効率化は、売上増の効果も期待できます。
今回は、中小企業経営者の皆さんが足元を見直すことでできるコスト削減のコツについて、経営支援のスペシャリストである中小企業診断士の西川邦広氏がお答えします。
中小企業からのよくある質問
無駄なコストの削減を進めたいのですが、何をどのように進めればよいかわかりません。
この質問に回答する専門家

中小企業診断士
西川 邦広
東京外国語大学卒業。ゼネコン勤務後、証券会社で海外駐在を含む31年間に、経営企画、企業再生、リスク/内部管理、介護施設運営他に関与。財閥系ゼネコンの社外取締役歴任。中小企業診断士。
目次
 売上が伸びているのに利益が出ない
売上が伸びているのに利益が出ない

赤字覚悟の一時的な販売戦略は別として、発生するコストを売上でカバーしていくコスト管理ができていないと最終的に利益は生まれません。
そもそもコスト管理ができていなければコスト削減はできないのです。
中小企業経営に占めるコスト
中小企業の売上高経費率は平均96.7%。最大97.9%(卸売業)、最小でも91.5%(不動産/物品賃貸業)とコストが占める比率は極めて大きいことが分かります(中小企業庁「中小企業実態基本調査/平成30年確報」の経常利益率より算定)。だからこそ僅かなコスト削減であっても、中小企業にとっては大きな効果があります。
コスト削減へのアプローチ
利益改善のために、中小企業の経営者がコスト削減に着目することは重要です。ところが帳簿を見ると、多くの場合一面に支出費目がずらっと並んでいます。これではどれが問題なのか、費目をひとつ丸ごと削減すればよいのか、見当がつきませんね。
ここで闇雲にコスト削減を行うのは賢明ではありません。通常、コスト削減というと事務所経費等の固定費に目を向けがちです。固定費の代表的なものが事務所人件費ですが、これを簡単に削減をしてはいけません。なぜなら、従業員の士気低下に繋がるからです。
それでは、どこからコスト削減を進めていくべきなのでしょうか。まずは日常の振り返りが大切です。
 こんな無駄や不要なことをしていませんか?
こんな無駄や不要なことをしていませんか?

日常業務を振り返ると、下記のような場面を見聞きしませんか? そこにコスト削減のヒントがあります。
日常業務に見える無駄の例
- いつもの顧客からの発注だから、いつも通り作っておこう →仕様違いによる手戻りで人件費・材料費等の無駄になります。
- まだ時期じゃないけど、取り敢えず仕入れておこう →不要不急の仕入の在庫積み上げになります。
- 紛失すると困る資料だからまずコピーをとっておこう →不要なコピー費用と無用な保管スペースを確保することになります。
- まずは集まって会議をやろう →目的や時限が不明確では時間の空費、他の仕事の機会逸失や事務所の非効率利用になります。
- この設備のほうが便利そうだから購入しよう →必要以上に高いスペックでは使いこなせず不稼働資産化になります。
人のふり見て我がふり直せ
職場で他人の行動などを見て、「ああ、もったいない」「要らないのでは?」と気になることがあるでしょう。ちょっとした無駄も放置すると積もりに積もって大きなコストになりかねません。
 コスト削減はどこから手を付けるか?
コスト削減はどこから手を付けるか?

身近な経費から始めよう
身近な経費(家庭で行われるような節電・節水レベル)から始めるのはひとつの手です。中小企業の場合は水道光熱費や、賃借料(事務所、倉庫、駐車場)・リース料・交通費・通信費・事務用消耗費・人件費(事務所)・諸会議費等の事務所運営経費などです。 通常は、経費総額あるいは各費目を、年度予算対比で行いコスト削減を進めます。
変動費と固定費
経営管理では、コストを変動費と固定費という区分けをして行うアプローチがあります。区分けをすることで利益管理が細かくでき、また個別製品の生産戦略等にも活用できます。 売上の増減に比例して変わる変動費(主に原価を構成する労務・材料・外注費など)は、コストを削減することによって大きく利益改善に寄与します。
前述の事務所運営経費は販売・一般管理費としてほぼ固定費と同義です。固定費の割合が大きい企業では、利益を確保するためコスト削減をして売上のハードルを下げなければいけません。
業務効率化
業務の進め方などを工夫することは、無駄な作業や行動を減少させ、関連コストの削減に繋がります。作業方法を標準化したり、業務手順の効率化、また最近ではIT導入による省力化も有効なコスト削減方法です。
 コスト削減に取り掛かろう
コスト削減に取り掛かろう

席が近い人たち数人によるグループ(部署別も可)でのブレインストーミングを通じて、日々気付いた無駄な作業の洗い出しと対策を繰り返し行います。経営者目線ではなく、地に足の着いた方法です。日々無理せず実行でき大きな効果が期待できます。
例えば社内向け資料のカラーコピーは禁止といったレベルから始めましょう。コピー原価を周知し、削減効果を共有していきながらコスト削減行動への意識を定着化させます。
マニュアル化による作業の標準化
マニュアル化は、コスト削減の代表的なアプローチで、定着化させていくことが肝です。そのため、経営者が主導していくことも必要です。
注意点として、中途採用者や未熟練者が読めばすぐ作業できるマニュアルでないと、かえって時間の空費や手戻りに繋がってしまいます。
マニュアルの遵守が常態化してはじめて、コスト削減の結果として現れます。
ITによる業務の効率化
マニュアルによる作業標準化と並行して、IT導入もひとつの方策です。業態、事業戦略、抱える課題等で導入技術は検討する必要があります。また対費用効果も考慮する必要があり、市販ソフトの利用も可です。 通信連絡、原価管理、資金繰り、顧客管理、労務管理など経営管理上優先する課題等を勘案してIT機器やソフトを導入しましょう。昨今では中小企業のIT導入を支援する補助金等の施策もあります。
コストの推移を見ましょう
経営管理の観点から決算数字によるコスト削減にも手を付けていきましょう。過去3年間(できれば5~10年間)の各費目の金額の推移を見て、自社の特徴を把握します。 突出した、あるいは急に増加した費用があれば原因を究明しましょう。併せて、各費目の対売上比率の変化を見ます。事業計画に沿って、売上増や体制強化に紐づけられるのかといったことを判別し、説明のつかない費目は削減しましょう。
経営指標の活用
決算数字を見ると、例えば、総資本売上回転率から効率性を評価して遊休資産の有無を確認できます。また、棚卸資産売上回転率から材料の適正在庫量などを検討する契機になります。このように、なかなか見えづらい事業運営上の無駄を発見することは資金繰りの安定にも繋がります。
人件費の削減は注意
前述の通り、人件費の一律な削減は士気低下、品質劣化の誘因となり得るため、注意が必要です。労働力の余剰は配置転換や育成による職種変更、また働き方改革で残業や休日勤務の見直し、IT導入といった効率化を検討すべきでしょう。
 コスト削減は客観的な視点で行いましょう
コスト削減は客観的な視点で行いましょう
コスト削減は不断の取り組みが必要です。事業活動はすべてコストと無縁ではいられません。中小企業の経営者は、経営指標で客観的な評価からコスト削減を行う発想が必要です。業務プロセスの見える化によるコストの発生状況、そしてコストが及ぼす利益水準への影響などを説明していくことが、コスト削減の定着化に繋がります。
専門家紹介

中小企業診断士
西川 邦広
専門分野
□ 事業計画(新規事業、創業、事業承継等)、資金調達、金融再生
□ 経営改善(課題発掘、行動計画作成とモニタリング)、組織活性化
□ M&A(買収、売却、廃業、事業連携等)
□ リスク管理、事業継続(BCP他)、内部管理体制
□ IPO(上場等)準備
自己紹介
東京外国語大学卒業。ゼネコン勤務後(原価管理、契約管理、労務、不動産開発等)、証券会社で海外駐在を含む31年間に、経営企画、企業再生、リスク/内部管理、介護施設運営他に関与。財閥系ゼネコンの社外取締役歴任。中小企業支援では建設/住宅設備/観光バス/外食/小売・卸/介護等企業の経営支援実績。中小企業診断士、宅地建物取引士、ロジスティクス管理士(物流)、CFP。資金調達や介護事業に関する執筆あり。東京都在住。
・この専門家の他の記事をみる
2020/2/20
2020/1/31
・このカテゴリーの他の記事をみる