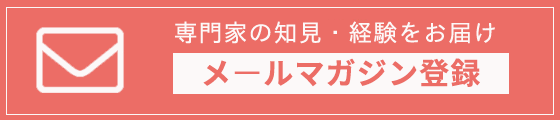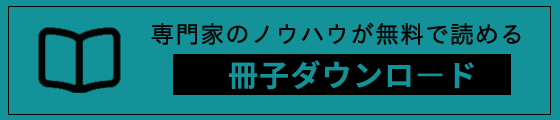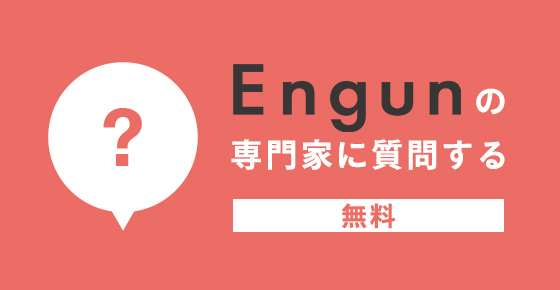経営企画・戦略立案
2019/12/23
中小企業が策定した事業計画を実行に移すために押えるべきポイント
![[中小企業が策定した事業計画を実行に移すために押えるべきポイント]トップ画像](https://cdn.2nd-pro.com/media/strategies-20191225-top.jpg)
事業計画を作っても、うまく実行できないと悩む中小企業経営者は多く存在します。それは従業員が付いてこない計画書になってしまっているからかもしれません。
今回は全従業員が一丸となって事業計画を実行していくためのコツについて、経営支援のスペシャリストである株式会社彩代表の西川邦広氏がお答えします。
中小企業からのよくある質問
事業計画は策定したのですが、実行できていません。事業計画を実行するために重要なポイント・コツを知りたいです。
この質問に回答する専門家

中小企業診断士
西川 邦広
東京外国語大学卒業。ゼネコン勤務後、証券会社で海外駐在を含む31年間に、経営企画、企業再生、リスク/内部管理、介護施設運営他に関与。財閥系ゼネコンの社外取締役歴任。中小企業診断士。
目次
 事業計画を作るだけでは経営目標は達成されない
事業計画を作るだけでは経営目標は達成されない

経営者と従業員の共感が重要
事業計画には、経営者の理念や思い、事業の方向性、目標とその達成方法などが示されます。これらに向かい全社一丸となって取り組むことが期待されているわけですが、従業員の理解のない計画は空転します。目標や手段に従業員が共感していますか。
従業員がさまよわないようにする
目標へ向かって歩む手順は示されているでしょうか。
例えば、友人たちとバーベキューをする時に、誰が何を買うのか、またいつ、どこで買揃えるのか、などのような役割分担をしませんか。
同様に、事業計画の目標達成の施策を、誰が、何を、いつ、どのように進めるのかを定めないと、各従業員は勝手に動いたり、最悪な場合は自分の役割が分からないままに何もしないということになります。
 従業員が付いてこない計画の特徴
従業員が付いてこない計画の特徴

従業員が付いてこないことで実行に至らない事業計画の具体例を列挙してみましょう。
経営者の独りよがりの計画となっているケース
①“こうしたい”、“こうあるべきだ”、など経営者の気持ちだけが全面に出ていると、従業員は「社長に任せよう」、「分かるけどね」といった受け止め方になります。
②事業方針や目標が明確にされていないと、従業員は「どこへ向かうのだろう」、「何をしたいのだろう」と不安になります。
③“とにかくやろう”、などといった抽象的な表現になっていると、従業員は「どうすればいいのだろう」と、一歩を踏み出せません。
④そもそも課題認識が共有されていないと、従業員からすると他人事になってしまいます。
⑤課題設定の背景が明らかにされていないと、従業員はどういう対策が適切なのか分かりません。
⑥従業員への説明がされていないと、従業員が理解できず、一丸となれません。
計画が絵に描いた餅になっている
①課題ごとの対策が明確になっていないと、従業員は何から手を付けるのか、何をするのか頭を抱えてしまいます。
②誰が、何を、どのように、いつまでにやるのか分からないと、計画は従業員にとって他人事となり、自ら行動してくれません。
③誰が推進役なのか、責任者なのか分からないと、統制がないことで計画がとん挫してしまいます。
このように、やるべきことが具体的にイメージできない計画は失敗します。
 計画は実行してこそ意味がある
計画は実行してこそ意味がある

ポイントは実現性の高い事業計画を作り、そして実行に移せるように手順を示した行動計画を作ることです。
事業計画の実行可能性を意識する
事業計画では事業の方向や目標を定めます。現在や将来の事業環境分析を基に、自社の強みを活かす戦略を採り、達成し得る目標としましょう。挑戦することは尊いのですが、過度の水準を求めず、従業員の達成満足度を高めることから始めましょう。
現在不足している経営資源を今後充足し、より達成を現実的なものとしていくことも必要です。
課題の適切な把握と対策
「この課題さえ解決できれば達成できる」という方策を見つけましょう。現状課題となっている原因を的確に突き止めることで見出せます。
その方策を着実に進めることで目標達成により近づきます。
行動計画を作る
ナビゲーションのようなものです。この道を進めば、いずれ目標に到達できそうだという感覚を各従業員に持たせることが必要です。
地に足ついた計画を実行して行くためには、大事な道具となります。
 計画を実行に移すコツ
計画を実行に移すコツ

ここでは事業計画をうまく進められず、とん挫する主な原因である行動計画に重点を置いてもう少し詳しくみていきましょう。
行動計画は全従業員で取り組む
行動するのは従業員ですので、事業計画への理解、課題認識の共有は不可欠です。課題への対策、その対策の行動(実行)計画を、従業員とともに経営者は作りましょう。計画の担当者も従業員の中から任命しましょう。社長ではありません。
優先すべきテーマを絞り込む
中小企業の経営では、課題が多く挙がるのは普通です。だからといってすべての課題に同時に取り組むことは賢明ではありません。緊急度や重要度から優先課題を1つ、多くとも3つに絞りましょう。
何よりも行動するというのが重要ですから、集中的に取り組む方が効果的です。
行動計画には具体的な数値計画を設定する
行動計画の中で大事なのが期限の設定です。いつ始めて、いつ終わるのか分からないようなやり方ではなく、期限を設けて着実に進めましょう。1年超を要するならば、複数の段階に分けるやり方もあります。
もう一つ大事なのが、成果指標(KPI)の設定です。道路でいうと地点標のような目安です。
例えばある課題に講じた対策の、3ヶ月後の目標達成率(%)/値(金額等)といった数値で、客観的に誰でも分かるものを設定します。内容次第では月、四半期を区切りとして設定しましょう。
モニタリングが肝
上記で設けた期限、指標を基に進捗を管理します(モニタリング)。
進捗管理者は計画担当者、あるいは別途その上席者でも良いです。モニタリング結果は全社で共有しましょう。
うまく進んでいないなら、その原因を追究しましょう。ここが計画の成否を握ります。そして結果を行動計画にフィードバックします。当初の設定計画値に無理があるなら総意の下、修正する勇気も必要です。ただし妥協はダメです。
 千里の道も一歩から
千里の道も一歩から
課題解決の取り組みは容易ではありません。だからこそ解決への道標が必要なのです。具体的に一歩ずつ進めるような手順や役割分担を決めて(=行動計画)進めましょう。
時には叱咤激励も必要ですが、途中の段階でも成果が確認出来たら喜びを分かち合うこともモチベーションアップになります。ジャンプせず、着実に歩を進めましょう。
専門家紹介

中小企業診断士
西川 邦広
専門分野
□ 事業計画(新規事業、創業、事業承継等)、資金調達、金融再生
□ 経営改善(課題発掘、行動計画作成とモニタリング)、組織活性化
□ M&A(買収、売却、廃業、事業連携等)
□ リスク管理、事業継続(BCP他)、内部管理体制
□ IPO(上場等)準備
自己紹介
東京外国語大学卒業。ゼネコン勤務後(原価管理、契約管理、労務、不動産開発等)、証券会社で海外駐在を含む31年間に、経営企画、企業再生、リスク/内部管理、介護施設運営他に関与。財閥系ゼネコンの社外取締役歴任。中小企業支援では建設/住宅設備/観光バス/外食/小売・卸/介護等企業の経営支援実績。中小企業診断士、宅地建物取引士、ロジスティクス管理士(物流)、CFP。資金調達や介護事業に関する執筆あり。東京都在住。
・この専門家の他の記事をみる
2020/2/20
2020/1/31
・このカテゴリーの他の記事をみる