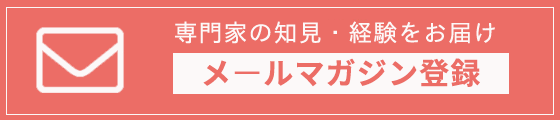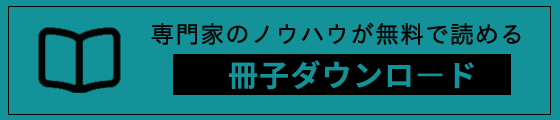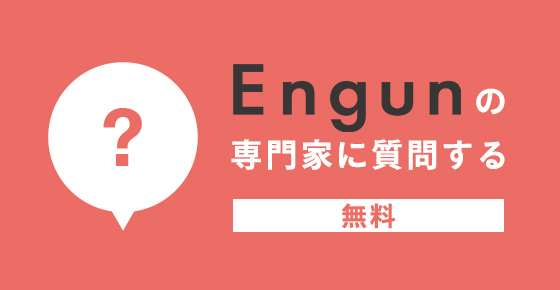情報化・IT活用
2020/1/9
属人化した業務知識・手順の可視化・伝承とIT導入
![[属人化した業務知識・手順の可視化・伝承とIT導入]トップ画像](https://cdn.2nd-pro.com/media/77e8acb0b50d7fc2f37f93845f341038_s.jpg)
中小企業においては、要員が少ないことから業務知識・手順が属人化しやすく、その人が欠けると社内の仕事が回らなくなるといったリスクが常にあります。また、この状況は企業成長の足枷でもあります。
本記事では、属人化した業務の可視化・伝承・IT化検討を、すきま時間でも可能とする方法について、複雑な業務プロセスの可視化・改善スペシャリストであるプロセス設計塾・代表 西本明弘氏がお答えします。
中小企業からのよくある質問
社内でミスやトラブルが増えており困っています。業務が属人化されているため、ミス・トラブルを起こす人と起こさない人が二極化しています。これらを改善する良い方法はないでしょうか?
この質問に回答する専門家

プロセス設計塾
代表
西本 明弘
小型トラック、プリンターの設計・開発20数年の後、3次元CAD導入コンサルとして設計手順(複雑な暗黙知)の可視化に従事。これを契機に、個人やチームの複雑な業務プロセスの最適化・技術伝承を支援している。
目次
 業務知識・手順の属人化は成長の足枷
業務知識・手順の属人化は成長の足枷

ベテランの業務がネック工程に
前述のような、「重要業務をこなせるベテラン」が一人しかいないと、そこがネック工程となります。会社がこなせる案件が制約され、成長の足枷となります。しかし、働き方改革の昨今、長時間残業という訳にもいきません。また、退職や病欠といったリスクもあります。
ベテランの業務が事業継続のリスクに
ベテランと若手との実力差によって、案件ごとに品質の差が生じると、お客様の信頼を損ねます。中小企業においては、社長の業務がネック工程の場合もあるでしょう。会社経営における商品開発、販売戦略、資金調達などの意思決定プロセスやノウハウが可視化されていないと、事業承継や合併問題が浮上した際の困難度合いが増すと考えられます。
 思考・意思決定プロセス(暗黙知)の可視化は後回し
思考・意思決定プロセス(暗黙知)の可視化は後回し

可視化(文書化)できればIT化できる
データ集計のように、手順が可視化できればIT化・効率UPの途が開けます。例えば、設計作業の自動化です。2次元CADから3次元CADに移行するとモデル作成の時間が増大するので、自動作図が望まれます。設計は暗黙的意思決定プロセスですが、ベテラン設計者の手順を可視化(作図プログラムの要件定義)することで自動作図を実現できます。さらに、手順が可視化されると他の設計者の知見も盛り込むことが可能となり、従来の”経験と勘”の世界に衆知を集めた進化をもたらします。
日本酒「獺祭」の躍進も可視化の賜物
獺祭で有名な旭酒造も、杜氏に逃げられたことを契機に、杜氏の”経験と勘”を科学的アプローチで可視化し、醸造技術を進化させてきたことが躍進の始まりだそうです。
 業務の可視化を会社のDNAとして定着させよう
業務の可視化を会社のDNAとして定着させよう
思考・意思決定プロセス(暗黙知)の可視化が後回しになるのは、ベテラン担当者が業務に忙殺され自分の手順を文書化している暇がない、また、思考プロセスを整理して文書化する方法もよく分からないからです。しかし、次節で説明する方法であれば、業務のすきま時間でも可視化ができますので、改善活動のテーマとして取り上げるなど、業務の可視化を会社のDNAとして定着させることが長期的視点で会社の成長に資することになります。
業務が回らなくなる前に地道にやろう
先ほどの3次元CAD導入による設計者の負担増や、ベテラン担当者の退職、マーケット急拡大で要員を増やしたいが教育資料がないなど、”このままでは業務が回らない”となってから”業務プロセスを可視化・見直そう”と思い立つケースがあります。日頃の地道な活動で業務プロセスが見えていれば、そのような事態にも対応しやすく、IT(RPAなど)導入検討の基礎資料にもなります。
 業務可視化の5つのステップ
業務可視化の5つのステップ

複雑な業務プロセスを記述するには、IPO:Input・Process・Output書式を使います。文章でだらだら書いたり、フローチャートを書くのではありません。IPOは、ISO9000の中でも推奨されています。まず、IPOで表現した小プロセス(Task)を地道に集め、ノウハウを明らかにすることが目標です。これなら、すきま時間でも可能です。
ステップ1.まずTaskを表出
可視化したい業務の塊を大プロセス、中プロセス、小プロセス(Task)へと階層的に木(Tree)構造に分解し、名前を付けます。WBS:Work Breakdown Structureという考え方です。
ステップ2.Outputデータ名を決める
各TaskのOutputデータ名を決めます。Outputが数十もあるようならTaskが大き過ぎるので、5個くらいに収まるよう分解します。普通、Task名と主要なOutputデータ名が同じになります。
ステップ3.必要なInputデータ名を拾ってIPO完成
TaskとOutputデータ名が出揃ったら、各Taskを実行するのに必要なInputをOutputデータ名一覧から拾います。欲しいデータがない場合は、推定出所を付記してInputデータに追加します。これでTaskの数だけIPOが集まりました。
ステップ4.Task実行のノウハウを付記
InputとOutputが決まれば、何をするTaskかが定義されるため、Task実行のノウハウを付記します。
ステップ5.授受されるデータ名でTaskを繋いで流れ(手順)を可視化
各TaskをデータのOut/In関係で繋ぐと、Taskの流れ(手順)が見えてきます。単純な1方向の流れならフローチャートを使えますが、流れが錯綜しTask数が多い場合は(複数部署連携を含め)DSM手法で流れを整理・改善するのが有効です。専門的になりますので、DSMの原理図だけ示しておきます。
ステップ5まで来ると、IT導入の基礎資料が完成です。システム開発の要件定義局面で重要なデータフロー図(DFD)と同等な情報が整備されますので、ITベンダーの費用を抑えつつ、業務にマッチしたシステムを発注できます。特許出願に例えると、アイデアだけ伝え弁理士に丸投げするより、明細書の骨子まで自分で書いた方が、弁理士費用を抑えつつ発明の意図が明確に伝わるのと同様です。

 属人化を脱して可視化経営に舵を切ろう
属人化を脱して可視化経営に舵を切ろう
業務知識・手順の可視化は企業成長への体質改善で、地道な取り組みですが、IPO作成だけでも3つの利点があります。
①社内で流通するデータ名が定義されます。”初期XX”や”1次XX”など、個人や部署によって用語が微妙に違ってはトラブルのもとです。Outputを出す人に命名権あり、とすれば社内用語が統一されます。
②若手が聞き取り役になってIPOを整備すれば、ベテランの負荷を減らしつつ知識伝承の場となり、冒頭の質問にあった二極化が改善します。
③複数部署でIPOを整備してデータの流れを可視化すれば、連絡漏れを防止し、フロントローディングも促進できます。
専門家紹介

プロセス設計塾
代表
西本 明弘
専門分野
□ 機械設計・開発
□ プロジェクトマネジメント
□ Design Structure Matrix手法による、複雑な業務プロセスの可視化・最適化
□ Analytic Hierarchy Process手法による、製品仕様の最適化
自己紹介
三菱自動車、IBMにて小型トラック、プリンターの設計・開発20数年の後、3次元CAD導入コンサルとして設計手順(複雑な暗黙知)の可視化に従事。これを契機に、複雑な情報連携プロセスの最適化・技術伝承をつうじてプロジェクト収益性の改善を支援している。支援においては、MITが主導しているDesign Structure Matrix手法を応用してお客様の負荷の最小化を図っている。この手法を2003年から自動車、エンジン、船舶などの設計・開発で活用しており、国内の草分けである。
・この専門家の他の記事をみる
2020/3/11
・このカテゴリーの他の記事をみる
2020/5/16
2020/5/16
2020/5/16